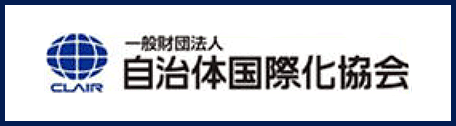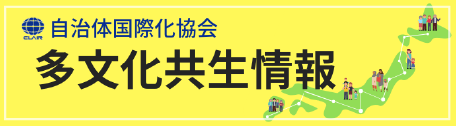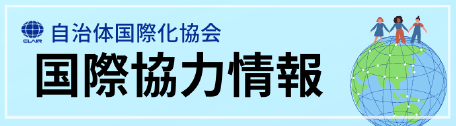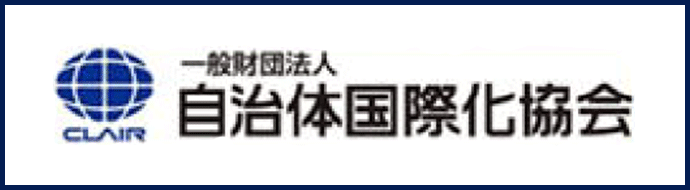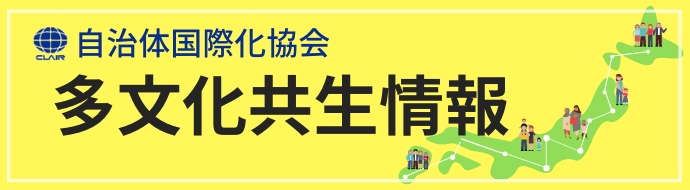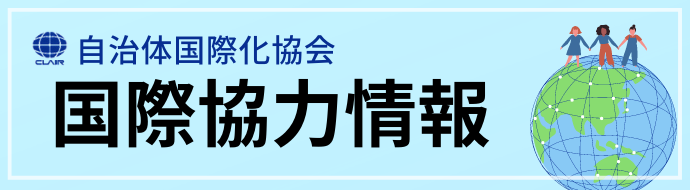令和7年度 国際協力推進セミナーを開催しました(オンライン)
国際協力推進セミナー
2025.09.26

令和7年度国際協力推進セミナー 報告書
地域発の国際協力 ~持続可能な未来を共につくる~
◆報告書のダウンロードはこちら
主 催:一般財団法人自治体国際化協会 市民国際プラザ
日 時:令和7年7月25日(金)13時30分~15時30分
形 式:ZOOMウェビナー
参加者:約124名(自治体、地域国際化協会、NGO/NPO、JICA、大学教員、学生、企業等)
<プログラム>
|
13:30-13:35 |
挨拶・主旨説明 一般財団法人 自治体国際化協会 交流支援部長 滝 仁和 |
|
13:35-14:05 |
話題提供「地域発の国際協力の意義」 認定NPO法人地球市民の会 プロジェクト・シニア・フェロー |
|
|
自治体国際協力促進事業(モデル事業) 事例紹介1 鳥取県庁生活環境部 脱炭素社会推進課 主事 土肥 瑞穂氏 |
|
|
自治体国際協力促進事業(モデル事業) 事例紹介2 愛媛県国際交流協会 森山 圭美氏 |
|
|
自治体国際協力促進事業(モデル事業) 事例紹介3 駒ケ根市役所総務部 企画振興課 地域政策係 主査 吉澤 啓太郎氏 |
|
14:50-15:15 |
質疑応答 |
|
|
国際協力促進事業(モデル事業)の概要説明とQ&A |
1.話題提供「地域発の国際協力の意義」
認定NPO法人地球市民の会 プロジェクト・シニア・フェロー 大野 博之氏
本講義では「地域発の国際協力」の本質と可能性について体系的に整理された。従来、国際協力は「開発途上国を援助する一方的支援」と捉えられがちだったが、地方自治体が取り組む国際協力は地域自身の課題解決や未来づくりにも直結する「戦略的な手段」になりえることも強調された。冒頭では、地域で国際協力を行う理由として、グローバル課題と地域課題の接点(気候変動、人口減少、外国人材の受け入れ、高齢化と介護人材不足、産業技術の承継など)が示され、国際協力を通じて地域の若者の地元離れ防止やシビックプライド向上が図られる例えも紹介された。また、行政と市民が共にプロジェクトを育てるためには「共感の醸成」が不可欠であり、その鍵として可視化(見える化)とナラティブ(主体的な物語性)、対話の仕組みが重要である。プロジェクト形成のプロセスとしては、1行政課題と地域資源の洗い出し、2課題と人材のマッチング、3新しい価値の創造という3段階が提示された。さらに、多様性(Diversity)、公平性(Equity)、包摂(Inclusion)を意味するDEIの視点を地域に導入する意義も説明され、住民参加の促進や行政への信頼構築に役立つとされた。成果の測定については、アウトプット(目に見える結果)だけでなく、若者の意識変容など社会的インパクト(アウトカム)に注目し、KPIを共有して参加型で評価する手法を推奨した。最後に、世界の人びとのためのJICA基金、クレアの自治体国際協力促進事業(モデル事業)、JICA草の根技術協力事業などの制度が紹介され、地域主体で持続可能な国際協力を実施する資金調達の選択肢も提示された。
2.自治体国際協力促進事業(モデル事業)
事例紹介1
「フィンランド共和国トゥルク市との学生等互派遣による気候変動対策に資する人材育成事業」
鳥取県庁生活環境部 脱炭素社会推進課 主事 土肥 瑞穂氏
鳥取県では、カーボンニュートラルの実現に向けた先進的な取り組みの一環として、フィンランド・トゥルク市との学生相互派遣事業を実施している。県は2030年度までにCO₂排出量を2013年度比で60%削減するという高い目標を掲げ、「鳥取エコライフ構想」を推進。これは「我慢する環境対策」ではなく、「快適な生活と環境保全を両立するライフスタイル」への転換を目指すビジョンである。令和5年度には、国際会議COP28への県内学生派遣が実現し、若者が気候変動問題を自らの課題として世界に発信した。現地での活動を通じて、トゥルク市との接点が生まれ、翌年度から本格的な学生交流が始まった。学生プラットフォーム「トットリボーン!ユース(TRY)」が結成され、事業の企画運営に主体的に関わる仕組みも整備している。この交流は単なる短期派遣にとどまらず、事業報告会やイベントを通じて県民全体に成果を還元し、若者が中心となって地域に新しい環境意識を広げている。また、県外の自治体や国際機関ともネットワークを構築し、他地域との連携・協働も視野に入れている。
資金面では、今年度はクレアのモデル事業を活用している。将来的には、単発交流から脱却し、他自治体の取り組みと連動した合同イベントやオンライン交流など多様な形態を導入し、持続可能な国際協力モデルとして進化させることを検討している。
事例紹介2
「愛媛スリランカ技術交流事業」
愛媛県国際交流協会 森山 圭美氏
愛媛県国際交流協会では、2006年からスリランカとの農業交流事業を開始し、「愛媛みかん」の栽培技術移転を軸に20年近く事業を継続してきた。きっかけは、スリランカ出身の留学生が愛媛みかんの品質に感銘を受け、「かつて自国にも甘くて種のない柑橘があったが病害で失われた」という声を職員が受けたことだった。クレアのモデル事業が自治体だけでなく、地域国際化協会も交付対象となったことも相まって、愛媛県国際交流協会は県の果樹試験場など専門機関と連携し、スリランカ農業省職員への技術指導を実施。事業の前半期(第1~4期)では、苗木の供給やみかんの栽培適地調査の実施、栽培技術研修を行った。中期(第5~6期)には、スリランカ農業省主導による柑橘栽培の普及を支援しつつ、スリランカ政府からの要望により水産加工技術指導を実施した。その後、西日本豪雨やコロナ禍といった困難を経て、県内で不足している農業分野の人材交流についてスリランカ政府関係機関との協議を重ねた結果、令和5年には「愛媛県とスリランカ民主社会主義共和国労働・海外雇用省との間の農業分野等における協力に関する覚書」を締結、スリランカからの農業人材を愛媛県に受け入れることにつながっていった。
この事業の特徴は、単なる技術提供ではなく、現地パートナーと対等な協働関係を築いた点にある。長期にわたる交流を通じて、国際協力が愛媛県の地域産業の持続可能性確保の糸口となっていった。さらに、事業の成果を県民等への普及啓発に活用できるよう広報子を作成、報告会などを通じて配布・周知しており国際協力の意義を広く伝えている。
事例紹介3
「母子保健研修センターにおける指導者養成事業」
駒ケ根市役所総務部 企画振興課 地域政策係 主査 吉澤 啓太郎氏
ネパール交流市民の会 プロジェクトマネージャー 北原 照美氏
長野県駒ヶ根市は青年海外協力隊訓練所を地域資源と位置づけ、市民主体の国際交流、国際協力を推進してきた。駒ヶ根協力隊を育てる会や、ネパール交流市民の会を中心に、ワールドフェスタ、中高生の体験入隊などを実施し、若者の国際感覚の育成も行っている。特に、平成13年に国際協力友好都市協定を結んだネパール・ポカラ市における母子保健プロジェクトは17年以上継続している。まず救急車や医療機材の寄付に始まり、外務省「草の根・人間の安全保障無償資金協力」で病院建設支援へと発展した。その後、JICA草の根技術協力事業として母子健康手帳の開発・導入、母乳育児支援のための乳房ケア研修を実施してきた。ネパール初の母乳外来開設や母子手帳普及など、出産・育児環境の改善に顕著な成果を上げてきた。クレアのモデル事業も活用したが、コロナ禍となり、結果としてオンライン研修の開発につながった。
この取組は医療専門家や企業の技術協力(民際協力)と、市民や学校による手作り品提供やオンライン交流(民際交流)を両輪とする民際活動である。9,000点を超える贈り物や研修支援を通じ、日本とネパール双方に喜びと誇りが生まれ、地域にいながら世界とつながる実感を醸成し、産官学民が垣根を越えて協力し合う「地域共創型国際協力モデル」という形を築いてきた。駒ヶ根市はこの経験を基に、多様な主体と連携し、持続可能な国際協力のさらなる発展を目指している。
質疑応答
「自治体ならではの国際協力の意義とは?」
土肥氏は、自治体が国際協力に関与することは、地域課題と世界課題の接点を見出し、施策の参考や刺激となる点が大きいと述べた。さらに、海外への関心は高いが行動のきっかけを持たない若者に対し、自治体が海外との接点を開くことで活動の選択肢を広げられると指摘した。
「NPO/NGOと自治体の協働メリットとは?」
北原氏は、自治体からの初期コンタクトや広報支援が協力を得やすくし、事業の認知度や参加者が広がると説明。取組みへの首長・議員の理解も深まり、他事業との連携や現地訪問につながる、公共施設が活用しやすいなど、活動の広がりが生まれると述べた。
吉澤氏は、市民が国際理解教育や社会貢献活動に参加できる機会が生まれる点を最大のメリットとした。NGOが顔の見える交流を続けているからこそ、行政も継続的な取組が可能になっていると評価した。行政と市民団体の関係維持の秘訣として、市が主導するのではなく、市民団体のやりたいことを尊重し支援する姿勢が長期的な協働の鍵であると述べた。行政課題と団体活動の方向性が合致している点も継続の要因とした。
「地域リソース活用のポイントは?」
森山氏は、事業の基盤として人材の存在が重要であり、長期的に関わるキーパーソンが組織の強みを活かし、地域資源を結びつける役割を果たしてきたと述べた。
総括 大野氏
国際協力は、他国、他者のための取り組みに限定されないものであり、地域の課題を解決するための有効なツールとなりえる。主体的に取り組むことが重要である。
3.国際協力促進事業(モデル事業)の概要説明&QA
最後に、(一財)自治体国際化協会 交流支援部経済交流課より自治体国際協力促進事業について説明が行われた。