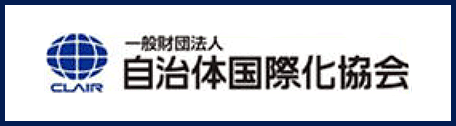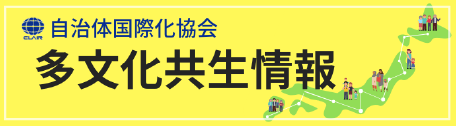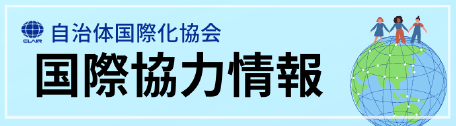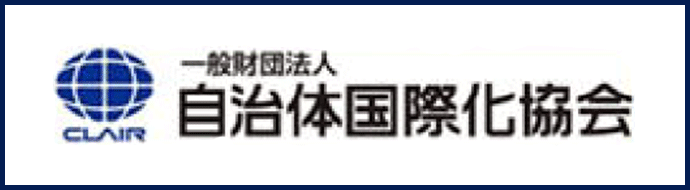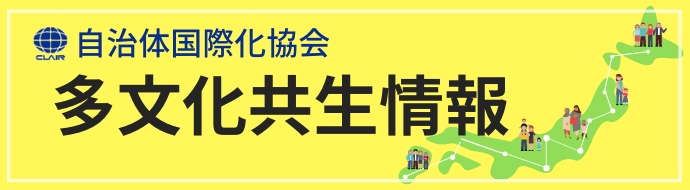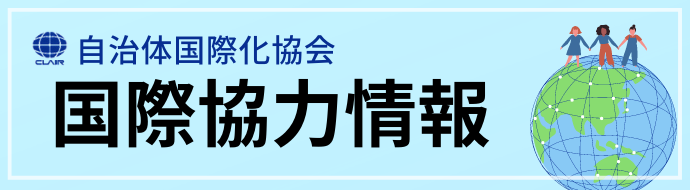令和6年度多文化共生の担い手連携促進研修会第一部を開催しました (オンライン)
連携推進セミナー
2024.12.24
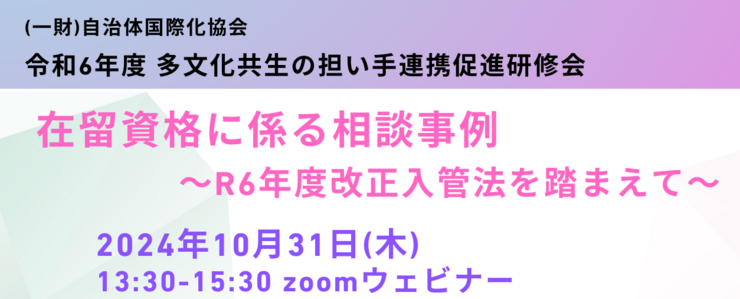
令和6年度 「多文化共生の担い手連携促進研修会」第一部 報告書
在留資格に係る相談事例 〜R6年度改正入管法を踏まえて〜
主 催:一般財団法人自治体国際化協会 市民国際プラザ
<プログラム>
| 13:30-13:33 | 開会 |
| 13:33-13:38 | 主旨説明 特定非営利活動法人多文化共生マネージャー全国協議会 代表理事 土井 佳彦氏 |
| 13:38-14:22 | 導入講義 東京出入国在留管理局 在留管理支援部門 北村 晃彦 氏 |
| 休憩 | |
| 14:25-15:25 |
パネルディスカッション パネリスト (公財)札幌国際プラザ 多文化交流部相談支援課 課長補佐 金子 幸恵氏 (公財)とやま国際センター 富山県外国人ワンストップ相談センター 相談コーディネーター 清水 文代氏 (公財)浜松国際交流協会 副主幹 キクヤマ リサ氏 (公財)佐賀県国際交流協会 主査 北村 浩氏 モデレーター (特活)多文化共生マネージャー全国協議会 代表理事 土井 佳彦氏 アドバイザー 東京出入国在留管理局 在留管理支援部門 北村 晃彦氏 |
| 15:25-15:30 | 総括 土井佳彦氏 |
| 15:30 | 閉会 |
主旨説明
特定非営利活動法人多文化共生マネージャー全国協議会 代表理事 土井 佳彦氏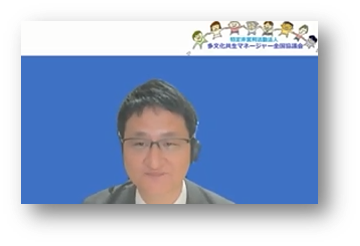
前半は東京出入国在留管理局の北村晃彦氏による導入講義を行う。後半のパネルディスカッションでは、本日の研修会の企画の策定のベースとなった多文化共生マネージャー等で構成される検討会のメンバーの中でも、日常的に外国人住民の相談業務に従事しているパネリストが、地域での支援事例を共有し、参加者から多数寄せられた質問について対応する。多くの方に参加いただき、質問も多かったための、すべてには回答できないことをご了承いただきたい。本日の研修会が、外国人支援に関する有意義な学びあいの機会となることを期待している。
導入講義
東京出入国在留管理局 在留管理支援部門 北村 晃彦氏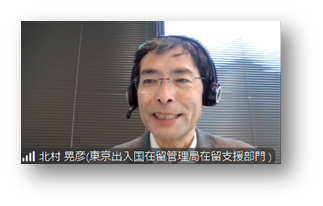
育成就労制度
令和6年の第213回通常国会で出入国在留管理関連の法改正が行われ、新たに「育成就労制度」が設けられた。この制度は、30年間実施されてきた技能実習制度の課題を踏まえ、外国人労働者のキャリアアップ支援と人材確保を目的としている。従来の技能実習制度は技能移転による国際貢献を目的としていたが、人権侵害や運用上の問題が指摘され見直しが求められていた。また、国内の労働力不足や国際的な人材獲得競争の激化も背景にある。
育成就労制度は、外国人労働者の育成と日本の産業を支える人材の確保を重視し、特定技能制度と連携することでキャリアパスを明確にする。3年間の育成就労期間を経て特定技能水準に到達することを目指しており、特定技能の産業分野と受入分野を一致させる方針。本制度の具体的な運用については未定の部分も多く、現時点で説明可能な範囲に限られることを了承いただきたい。
育成就労制度においても育成就労実施者は個々の労働者の育成就労計画を策定し、現在の技能実習機構に替わり設置される予定の外国人育成就労機構が認定する。また、従来の監理団体の代わりに「監理支援機関」が設置され、外国人労働者の適切な雇用管理や保護が行われるようになる。技能実習制度においては一部の監理団体が独立性中立性の観点で適切に役割を果たしていないという指摘があったことを受けて監理支援機関は受入れ機関との利害関係がない独立性を確保し、外国人労働者の転籍支援や保護の中心的役割を果たすため、その認可はより厳格化する予定である。また、送り出し国との二国間協定を締結し、外国人が負担する手数料の適正化が進められ悪質な送り出し団体の排除が強化される想定である。
育成就労制度のもう一つの特徴は、外国人労働者が自らの意思で転籍が基本的に認められる点である。これにより外国人労働者の人権が尊重される。転籍には一定の条件が設けられ、監理支援機関やハローワークの支援を受けられる体制が整備される。育成就労制度は令和9年4月から6月頃の施行が予定されており、経過措置として施行日以前に来日した技能実習生は従来の技能実習制度で在留を継続することを可能とする予定である。
永住許可制度の適正化
永住資格は永住許可を受けた後、在留期間の制限無く滞在できる資格であるため、永住許可を得た後は在留審査等が行われない。そのため、永住許可を得た後に、税金や社会保険料などの公的義務を怠る事例が増加していることを背景に、許可基準の明確化と取り消し制度が定められた。具体的には、永住者が義務を果たしているかを確認する仕組みが導入され、公的義務の未履行や重大な刑罰法令違反があった場合、永住許可の取り消し対象となる。ただし、病気や失業など本人の責任外での不払いは考慮され、軽微な違反が直ちに取り消しにつながることはない。取り消し手続きにおいては十分な調査と意見聴取が行われ、必要に応じて他の在留資格への変更が認められる場合もある。また、永住許可の取り消しが即時の退去を意味するわけではなく、悪質なものを除いては、定住者など他の在留資格に変更されることが想定されている。
パネルディスカッション
パネリスト
(公財)札幌国際プラザ 多文化交流部相談支援課 課長補佐 金子 幸恵氏
(公財)とやま国際センター富山県外国人ワンストップ相談センター 相談コーディネーター 清水 文代氏
(公財)浜松国際交流協会 副主幹 キクヤマ リサ氏
(公財)佐賀県国際交流協会 主査 北村 浩氏
アドバイザー
東京出入国在留管理局 在留管理支援部門 北村 晃彦氏
モデレーター
(特活)多文化共生マネージャー全国協議会 代表理事 土井 佳彦氏
在留資格に関する相談対応をテーマに、参加者から事前に寄せられた質問等に基づいて、各地で相談対応を行っているパネリストにより具体的な事例について共有、意見交換が行われた。
導入講義で説明された「育成就労制度」や「永住資格の取り消し」に関しては、パネリストが実際に受けた相談や地域での関心事が取り上げられた。技能実習から育成就労への移行に伴い、外国人労働者や雇用企業から、制度変更が業務にどのような影響を与えるかについての問い合わせが増え、制度の詳細が固まるまで情報提供に限界がある現状が共有された。また、永住資格の取り消しに対する不安も根強く、税金の滞納等に関する相談等が寄せられていると報告された。
離婚や婚姻に関する問題では、特に外国人女性が日本人配偶者からのDV被害に遭うケースや、在留資格や親権を巡る問題が深刻化していると述べられた。パネリストは、DV被害者の相談先として地方入管も挙げ、在留継続の可能性について説明するなどの対応方法が示された。また、日本人配偶者が勝手に離婚届を提出するという事例もあり予防措置を取れる「離婚届不受理申出」の情報が紹介された。さらに、婚姻に伴う家族の呼び寄せについても議論され、高齢の親を日本に呼ぶことが難しい現状や、特定活動の在留資格の取得条件の厳しさについて意見交換が行われた。
生活や住居に関する問題では、雇用のミスマッチにより来日後すぐに職を失い、住まいも失った事例が共有され、在留資格申請の際に費用支弁能力を問わない「技術・人文知識・国際業務」などは、貯金もなく来日する人もいることから、職を失い、お金も家もないというケースが今後増える可能性があるため支援体制の整備が望まれるとされた。民間団体が提供するシェルターはあるものの、全国的に対応施設が少なく、地方からも支援要請が寄せられていることが共有された。公共の支援も一部存在するが、短期間の利用に限られることが多く、長期的な支援を確保するには課題が残されている。
起業や経営に関する相談も増加傾向にあり、特に円安を背景に、経営管理ビザで来日する外国人が増加傾向にあり、ビジネスに関する相談が寄せられることもあるが、一元的相談窓口はあくまでも「生活相談」であるため行政書士や商工会議所などを案内するが、外国人に対して多言語で対応できる専門のビジネス相談先がない地域が多く、今後の改善が期待される分野とされた。
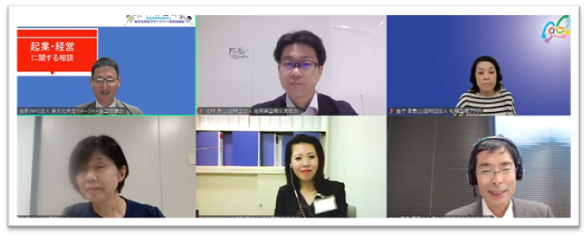
総括 土井佳彦氏
外国人住民に関する制度の周知について、国や入管庁の役割への期待が示される一方、ディスカッションで議論された様々な相談事例および事前に寄せられた数多くの質問を踏まえ、日常的に住民と接する自治体や国際交流協会、NPOの相談窓口等でも正確な情報提供を通じて不安を軽減し、安心できる環境を整える重要性がある。そのためには、情報交換により他者の経験を共有し、解決策につなげることが有効であり、今後の支援体制の強化や多様な連携に向けて、今回の研修会のような共有の場が継続的に持たれることに期待する。
以上