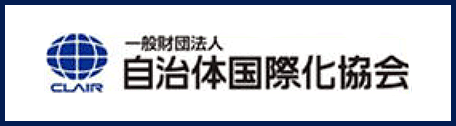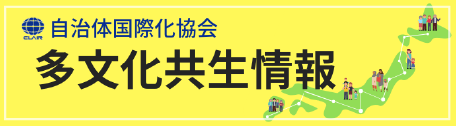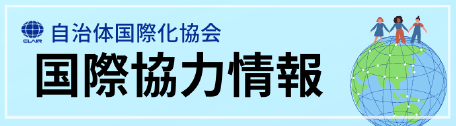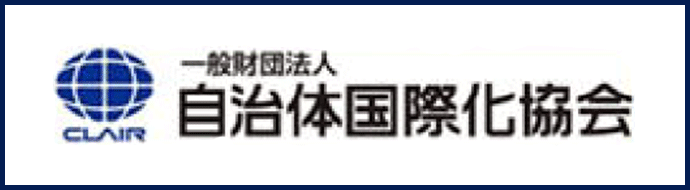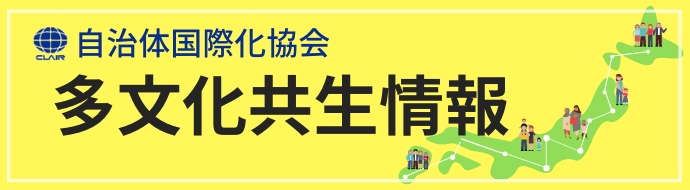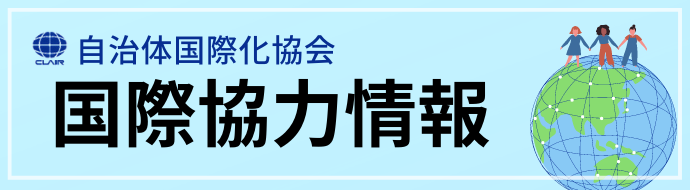令和6年度 国際協力推進セミナーを開催しました(オンライン)
国際協力推進セミナー
2024.10.18
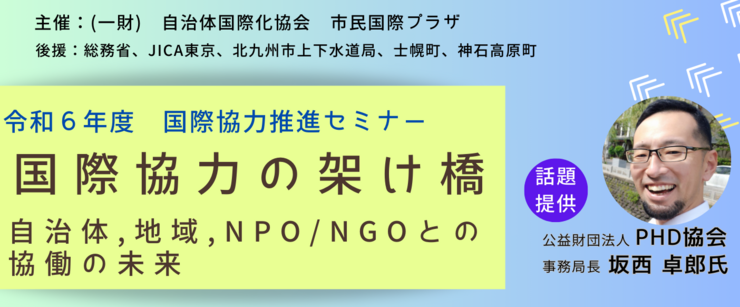
令和6年度国際協力推進セミナー 報告書
国際協力の架け橋~自治体、地域、NGO/NPOとの協働の未来
◆報告書のダウンロードはこちら
主 催:一般財団法人自治体国際化協会 市民国際プラザ
日 時:令和6年7月30日(木)13時30分~15時30分
形 式:ZOOMウェビナー
参加者:約98名(自治体、地域国際化協会、NGO/NPO、JICA、大学教員、学生、企業等)
<プログラム>
|
13:30-13:35 |
挨拶・主旨説明 一般財団法人 自治体国際化協会 交流支援部長 滝 仁和 |
|
13:35-14:00 |
話題提供「PHD協会の国際協力、国際交流、多文化共生」 公益財団法人PHD協会 事務局長 坂西 卓郎 氏 |
|
|
自治体国際協力促進事業(モデル事業) 事例紹介1 北九州市上下水道局 広域・海外事業部 係長 松原 寛之氏 |
|
|
自治体国際協力促進事業(モデル事業) 事例紹介2 |
|
|
自治体国際協力促進事業(モデル事業) 事例紹介3 (特活)ピースウィンズ・ジャパン ネパールプログラム チーフ 束村 康文氏 |
14:45-15:05 |
質疑応答 |
15:05:15:09 |
総括 公益財団法人PHD協会 事務局長 坂西 卓郎 氏 |
15:10-15:27 |
国際協力促進事業(モデル事業)の概要説明とQ&A |
1.話題提供
◇「PHD協会の国際協力、国際交流、多文化共生」
公益財団法人PHD協会 事務局長 坂西 卓郎 氏
国際協力の意義、在り方、昨今の潮流についてPHD協会の取り組みを踏まえながら話題提供が行われた。近年国際協力の概念が変化し、従来は国際協力と言えば主に日本から開発途上国への支援を意味していたが、近年では国内の外国人支援も国際協力の一環として考えられるようになり、国内での外国人支援と国際協力との境界が曖昧になりつつある。国際協力のアクターとしても、自治体やNGO単体ではなく、両者が連携したり、地域のアクターの連携による取り組みも行われており、具体的な事例がこの後紹介される。更に、コロナ禍を経て、国際協力NGOによる国内の多文化共生等への取り組みも一般化しつつあることも言及された。
PHD協会ではネパールなどアジアから日本への研修生受け入れて国内で実施する国際協力事業にも長年取り組んできた。市民主体の国際協力であり、様々な人を巻き込み「迷惑をかける」ことが受援力の高い市民参加の国際協力活動につながると説明された。開始当初は高いハードルとなった欧米以外からのホームステイ受け入れも現在はスムーズに進むなど、国際協力事業を通じて地域の人々と研修生の草の根の交流が継続している。そして2020年には「国際協力交流シェアハウス みんなの家」を設立するなどPHD協会としても国内の難民や困窮外国人の支援開始し、そのことによって自治体や国際交流協会との連携も開始した。具体例としてPHD協会、FMわぃわぃがJICAのNGO等活動支援事業として、外国人が福祉につながりにくいという課題解決のため、兵庫県三田市で行われた社会福祉協議会と国際交流協会の連携事業についても紹介された。更に、国内で外国人支援に取り組む経験が、将来的には海外での国際協力にもつながっていく可能性が示唆された。
質疑応答では、「地域の共生社会づくりと、地域の活性化をつなげる切り口」について質問があり、神戸で受入れてきた難民、例えば製菓会社として著名なモロゾフ氏の活躍など、国際協力が地域の多様性を生み出し、経済的なインパクトを含む地域の活性化につながる事例が示された。
2.自治体国際協力促進事業(モデル事業)
事例紹介1
◇ベトナム国ハイフォン市における浸水被害軽減のための組織強化プロジェクト
北九州市上下水道局 広域・海外事業部 係長 松原 寛之氏
北九州市上下水道局の国際協力事業の概要と、市の姉妹都市であるベトナム・ハイフォン市で行っている「浸水被害軽減のための組織強化プロジェクト」が紹介された。北九州市の上下水道局が、ハイフォン市における浸水被害を減らすために技術支援や現地職員の育成を行っている。
北九州市の国際協力事業は30年以上の歴史を持ち、上下水道局では1990年に西アフリカ・マリ共和国にJICA専門家として職員を派遣したことから始まった。その後、アジア各国への支援を強化し、現在はベトナムやカンボジアを中心に事業を展開している。この背景には、北九州市上下水道事業基本計画で掲げられた国内外への貢献の一環として、海外事業が位置づけられていることがある。国際協力事業の実施によって相手国の職員の能力向上や生活環境の改善を図ると共に、市職員の技術力向上を図っている。そして、相手国との信頼関係の構築により、地元企業のビジネスにつなげている。そのために、北九州市海外水ビジネス推進協議会という官民連携による水ビジネスの推進体制も全国に先駆けて構築した。また、市役所内では上下水道局海外事業課職員のみならず、他部署の職員が通常業務と並行して国際協力事業にも携わる形態となっている。
ハイフォン市での事業は2009年の友好・協力協定締結により上下水道の技術交流が活発化したことを背景として開始した。下水道分野では、2010年にハイフォン下水道排水公社と締結した「下水道分野における技術交流・協力に関する覚書」に基づいて、JICA草の根事業(2012年~2024年)フェーズ1からフェーズ3にわたって下水道施設の維持管理、下水処理場の運転支援、市民と共同による浸水対応訓練等が行われてきた。ハイフォン市では下水処理が開始されたばかりで、また、近年の気候変動の影響による大雨による浸水被害の頻発し、浸水被害が継続して起きており、今後も下水道分野の支援が必要である。クレアの「国際協力促進事業」としては、浸水被害軽減のための組織強化を目的に、JICA事業のフェーズ3で実施した住民と協力して浸水被害に対応するための訓練を、実際の大雨時に行動するための体制表の整備等を計画している。事業終了後は、デジタル技術を活用したインフラ管理の強化も視野に入れた活動への展開が期待されている。
事例紹介2
◇フードバリューチェーン学習を軸とした「士幌町インターンシッププログラム」による士幌町とキルギスの人材育成・地域交流事業
士幌高等学校 教諭 山﨑 恒氏、教諭 佐藤 正三氏 コーディネーター 古茂田 柴乃氏
北海道士幌町とキルギスとの間で行われている人材育成および地域交流事業について紹介された。この事業は、北海道士幌高等学校とキルギスの農業カレッジが連携し、フードバリューチェーンを学ぶインターンシッププログラムを通じて行われた。士幌町とキルギスのつながりはキルギスにもある「シーベリー」を士幌高校で栽培していることをきっかけに始まった。士幌高等学校ではシーベリーを使った特産品の開発が行われており、これがキルギス側の関心を引き2019年に交流がスタートし、士幌高校教員と(株)Cheers職員が現地に渡航した。その際クレアの「国際協力促進事業」が活用された。2021年から2024年にはJICA草の根事業としてキルギス農業カレッジとの農業教育プロジェクトが実施された。2023年には再度クレアの「国際協力促進事業」を活用し、キルギス農業カレッジの生徒と、士幌高校との生徒のオンラインも併用した交流により、双方の生徒たちはフードバリューチェーンに関する学びを深め、さらにパッケージデザインや商品開発についても共同で取り組んだ。また、キルギスでの活動の一環として、キルギスのブランド認証コンペに参加し、シーベリーを使った商品が高い評価を受け、今後はキルギスでのOEM製造や試験販売が予定されている。今後の展開として、共同開発した商品を士幌町やキルギスで販売する計画が予定されている。さらに、プロジェクトを通じて得られた経験や成果をまとめた手順書の作成が進められている。最後に、士幌高校生徒の西潟さんからも、キルギスとの交流事業が有意義なものであったことが報告された。
事例紹介3
◇「神石高原町を拠点にしたアジア地域の農業人材育成事業」
(特活)ピースウィンズ・ジャパン ネパールプログラム チーフ 束村 康文氏
神石高原町との連携事業について紹介された。ピースウィンズ・ジャパン(以下PWJ)は、広島県の神石高原町を拠点とする国際協力NGOで、災害支援や開発支援、人道支援を行っている。2015年のネパール大地震を契機に、ネパールでの緊急援助活動を開始し、その後、復興支援や地域の課題解決に取り組んできた。特に、農業分野での技術支援が中心であり、農村部の住民が持続可能な農業を実践できるよう、技術指導や短期研修を行っている。クレアの「国際協力モデ促進事業」を活用し、PWJは神石高原町と連携してネパールからの研修生を日本に招き、広島県内での農業研修を通じて技術の習得を支援している。この取り組みは、ネパールの地域課題の解決に寄与するだけでなく、日本の農業人材不足にも対応することを目指している。また、研修を通じて地域住民や農業関係者とのネットワークが形成され、地域社会の発展にも寄与する側面を持つ。さらに、PWJは地域との協力を重視し、研修生が地域社会に溶け込むことを目指している。研修生は、農業技術の習得だけでなく、地域の行事や活動に参加し、地域社会の一員としての役割を果たすことが期待されている。更には地域に根ざした人材育成と国際協力の両立を目指し、都市部に流れがちな外国人材の受け入れにもつなげたいと考えている。試行錯誤を続けながら、双方の地域課題の解決に向けた取り組みを進める予定である。
質疑応答
「自治体、団体、学校等が協働で行う国際協力のノウハウと、連携のコツについて知りたい」という質問に対して国際協力の成功の鍵として、カウンターパートとの信頼関係の構築が挙げられた。日本側の考えを一方的に押し付けず、相手国の立場に立って一緒に考え、持続可能な形でプロジェクトを進めることが重要であるとされた。行政や組織間の序列や慣習への配慮も求められ、これが円滑な連携の一助となる。
「連携のコツ」としては、地域の力を最大限に活用する点が強調された。特に、学校や自治体が地元の人々と密接に連携することで、相互作用を高め、持続可能な協力体制が築かれるとされた。技術や知識の共有がプロジェクトの成功に貢献することも述べられた。
「自治体ならではの国際協力、海外への貢献」という質問に対して、自治体が国際協力において持つ特有の役割、例えば、上下水道の運営に関するノウハウは、特に自治体が強みを持つ分野であり、これを海外に展開することで現地の水環境の改善に寄与することができる。日本企業の技術や製品をアピールする機会としても国際協力が活用され、実際にセミナーなどを開催し、日本の技術を広める取り組みが進められていると述べられた。
「高校生や大学生ができる国際協力」として、海外からの研修生と連携し、技術や文化を共有する機会が挙げられた。また、スマートフォンなどの最新技術を活用して学生同士が国際交流を深める姿が紹介され、こうした交流が生徒の成長に大きく寄与していることが述べられた。
「自治体が国際事業を行う際のパートナー選定のプロセス」についての質問に対しては、姉妹都市関係や地域の特徴を考慮したパートナー選定が強調された。自治体としても姉妹都市関係が基盤であると市民の理解も得やすい。信頼関係の構築が長期的な協力関係を支え、双方に利益をもたらす結果に繋がるとされた。
坂西氏による総括
地方自治体が国際協力に取り組む意義としては、北九州市の事例のように中央政府ではなく地方自治体が有する知識、技術、経験の共有や、士幌高校や神石高原町のように住民が参加することによる人材育成や意識啓発が挙げられ、両者の共通項として人材育成であるとされた。また、SDGsが掲げる「先進国も役割や責任を担う」という枠組みにより、国際協力が単に途上国を支援するものではなく、先進国側にも変化が求められるなど双方向性が強まっている。また日本国内もリソース不足により途上国への支援のみを目的とするのではなく、両者がwin-win、国内の人材も同時に育成されるような双方向性を持つこと、そうした人材が地域、日本、世界で活躍することが地域の活力や持続可能な発展に貢献することが、国際協力を通じて得られる可能性として期待が述べられた。
3.国際協力促進事業(モデル事業)の概要説明&QA
(一財)自治体国際化協会 交流支援部 経済交流課職員の宮内より、モデル事業の概要および申請方法についての説明が行われた。